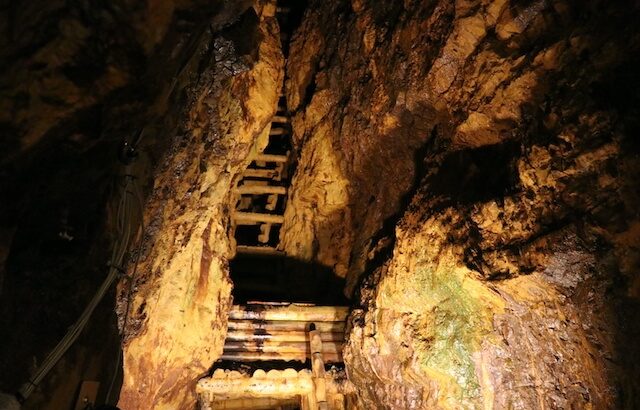芸術の評価というのは難しい。なぜなら大部分が観る者の主観に依拠してしまうからだ。
前置きのようにこんな評価基準を述べるのは、自らの主観に基いた暴論をぶちまける前触れだと思って頂いて結構だ。では、簡潔に、結論から述べよう。
ブリューゲルの『バベルの塔』(1565年)は間違いなくフランドル絵画史に燦然と輝く大傑作だ。
もうこれでほぼ私の言いたいことは終わっているに等しい。故にこれからしたためられるレポートや駄文は蛇足の感すら漂う。なので先に言っておく。以下は紙幅をただ埋めるためのものである。
ブリューゲル、「バベルの塔展」へ

2017年初夏、東京、上野。
ようやく念願のバベルを拝むことが出来る。オランダまで行かなければ見ることができないと思っていたものが、向こうから来てくれるなんて。しかも東京から大阪へと場所を移してほぼ半年日本にいるそうな。私は無駄にオランダ人の心配をしてしまう。今日本にあると知らずにボイマンス美術館に足を運んだユーロ圏内のバベルファンがその場で頭を抱えていないかなんてことを考えながら会場に足を踏み入れた。
彫刻の数々から展示は始まり、キリスト教の信仰を反映した絵画へと繋がり、一時代を築いたヒエロニムス・ボスの作品がフランドルに及ぼした影響を確認しながらクライマックスのバベルへと向かっていく。
ボスとブリューゲルが体系的に見られるということで二度美味しい企画ではあるのだが、個人的にはバベルが気になりすぎて気持ち的にボスを堪能する余裕が無い。ボスは再訪時にじっくり見るしか無いか。しかし独創的で奇妙なモンスターをあの時代に多数生み出したボスはもっと評価されるべきだ。特に日本で。
そしてついに、実物のバベルの塔と対面した。
59.9 x 74.6cm 油彩。思い焦がれた絵は思ったより小さかった。

思い入れが強すぎてフラットに語れないというのは冒頭に記したが、客観的事実としては、とにかく細部の書き込みがすごい。工事のために組まれた足場や、船から荷を積み下ろすクレーンなど、ディティールへの拘りは相当なものだ。一説にはこの絵には1400もの人物が描かれているという。ブリューゲルにとって晩年の作品なのだが彼に衰えという文字は無縁だったようだ。
極力脚色を避けてお伝えするのが記事の真摯な態度だと思うのでありのまま書くと、私はずっと「やばい」を連呼していた(急に若者)。やばいがNGワード、罰金一回5000円だったら私はきっと全財産を失っていただろう。
外に出ても、少しの間心ここにあらずだった。知らぬ間に手には図録の入った袋を持っていたし、無意識すぎるけどいつの間に買ってたのだろうか。やはりバベルやばい。
バベルの塔とは
さて、順番が逆のような気もするがバベルの塔について説明しよう。
旧約聖書にそのモチーフを得るバベルの塔は、ノアの子孫達が築こうとした塔だ。畏れ多くも天まで届かせようとしたため神の怒りを買い、彼らが協力してこのようなことを成し遂げようとするのは話している言語が同じであることが理由であるとして神によって彼らの言語は複数に分けられてしまった。
バベルは、ヘブライ語で「混乱」を意味するとされている。また、結局塔は完成せずに崩れてしまったことから、「実現不可能な計画」の代名詞ともなっている。
旧約聖書を額面通り受け取って、バベルのせいで言葉・民族が分けられたのならば、今ある争いの根源はこの建物だ。
そう、この塔はディスコミュニケーションの象徴だ。あなたが誰かとわかり合えないのはバベルのせいだ。或いは、学生時代外国語の授業に苦しめられるのも、大人になってさえ他の言語に苦しめられるのもバベルのせいだ。…さすがにそれは転嫁しすぎだろうか。
ブリューゲルは生涯で三度に渡りバベルの塔を描いてきた。
ひとつは現存しておらず、残りの二つのうち先に書かれたのが「大バベル」、もうひとつが今回来日した「小バベル」である。大小は単純に絵の大きさのことでありいずれもタイトルは「バベルの塔」だ。
私にとってのバベルの塔
タバコの似合う女性だった。その人は私よりも6〜8歳ほど歳上だったと思う(記憶が曖昧なのは年齢をさして重要視していなかったからだ)。あれはもう10年以上前のことだ。進学の為に上京し生活費をアルバイトで稼いでいた私は出来たばかりの原宿のバールで働いていた。彼女はそこの社員だった。社員という言葉が似合わないほど、どこか浮世離れした人で、すらっとした四肢と170を超える程の長身、艶のある長いストレートの黒髪が印象的だった。前職はモデル、と聞いてさもありなんと思ったものだ。
文句ない立地でありながらなぜか客がさっぱり入らないその店は、バイトの人数も少しずつ減らされ「ドリンクを一通り作れるから」というもっともな理由で私だけがいつもシフトに入れられていた。結果、その女性と二人きりになることが多かった。
いったい誰がここでプレイするんだ?と従業員一同不思議に思っていたターンテーブル(勿論2台、きっちりミキサーもあった)で営業終了後に音楽を流しながら何気ない会話を一頻りして帰るのが日課だった。
「最近、何かいけてるの無いですか?」
LAVAZZAのマシン洗浄を終えた私は瓶に入ったビスコッティをひとつ口に入れながら(売り物だったが、もう時効だろう)彼女に尋ねた。何か、というのは曖昧な質問な気もするがそれでもいつも彼女は適切な答えをくれた。音楽のときもあったし、映画のときもあった。有り体に言えば「センスが良い」人だった。
「あ、今あれやってるよ。コヤニスカッツィとポワカッツィの続編。ちょうど渋谷」
彼女との会話の中にはわけのわからない単語がたくさん出てきた。わからないことを教えてもらうと毎回嬉しかった。背伸びをする気持ちでその人の紹介してくれた作品を手に取ったりしていた。
で、さっきから一体何の話をしてるんだ?とお思いだろう。大丈夫、バベルの話だから。
例の教えてもらった映画を見に、まだ桜丘にあった頃の渋谷ユーロスペースまで一人で赴いた。タイトルは「ナコイカッツィ」、始まった途端にスクリーンに映し出されたのが、そう、ブリューゲルのバベルの塔だった。コラージュのような作品で、台詞もなく、ただ不穏な空気の中音楽と映像を浴びせられた。ひたすら不安になる映像と、鳴らされるチェロ。ミニシアター初心者にはいきなりレベルが高すぎて眉間に皺を寄せながらわかったつもりになろうとしていた。が、正直、良くわからなかった。わからないなりに自分の中に強烈に印象づけられたのがあの絵だったんだ。
後日、シフトが一緒になった時も気後れして映画を見に行ったことが言えなかった。高尚な感想を求められたらどうしようという逃げだったのかもしれない。今思えば、普通に行きましたよって言えば良かったと思う。バベルの絵が印象に残りましたね、ってただそれだけ言えば良かった。
そんな彼女は、そこから一月もせずに居なくなった。急に仕事に来なくなったのだ。幻滅するよりも、あの人らしいな、って思った。
おわりに
…放っておくとどこまでも筆が走ってしまいそうだから、自戒を込めて思い出話はこの辺にしておこう。どこにでもありそうな背伸びのシークエンスは歓迎されなそうだから。ともあれ、それ以来バベルがずっと心の中にある。
調べれば調べるほど、この絵の暗示しているものやストーリーに興味を持った。日本に来たことがあるらしいが24年も前のことだったそうだ。いつか見に行けたら、そんな絵だったのだが…
「2017年、日本に来るってよ。」 ー これこそが、鳴り響いた天啓のラッパだった。

見に行ってからもうひと月ほど経つが、相変わらず見返している。